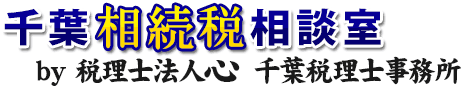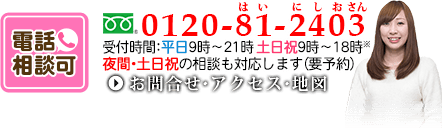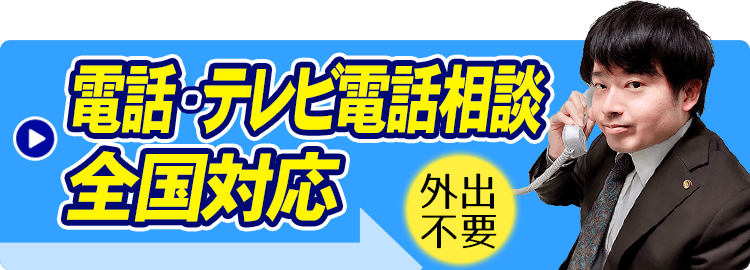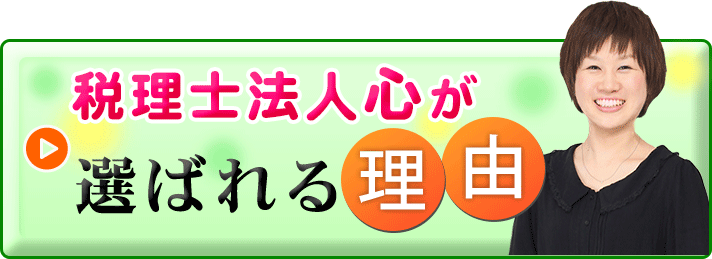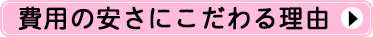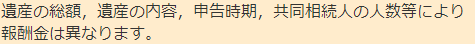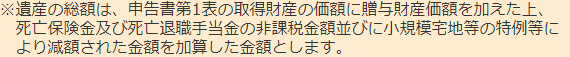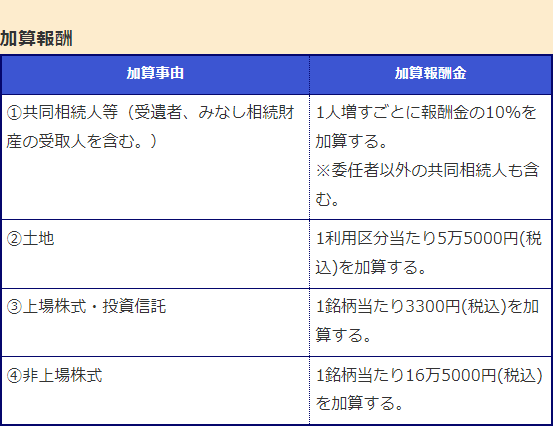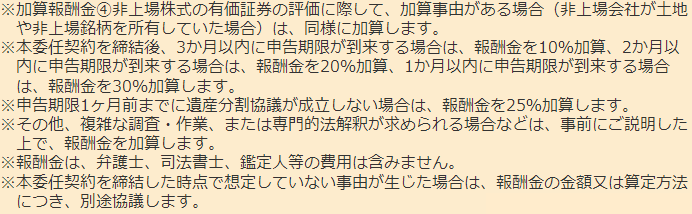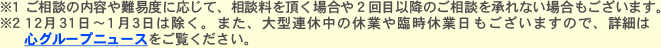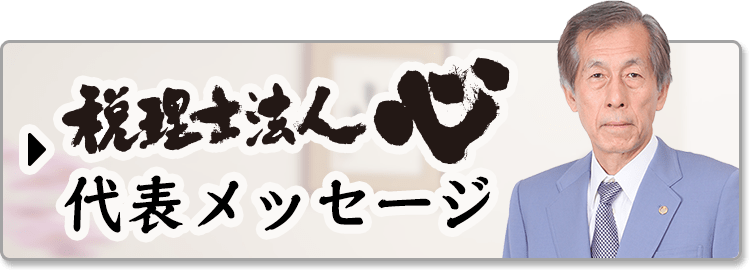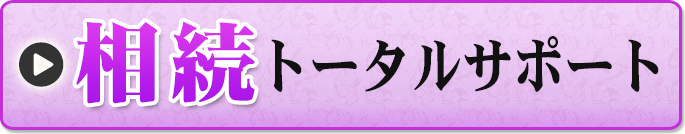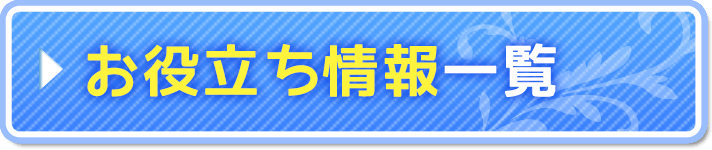お役立ち情報
夫婦間の贈与
1 夫婦間でも贈与税がかかる場合があります
夫婦で一緒に生活をしていると、日常の買い物や旅行などで夫婦間のお金や物のやり取りはよくあることだと思います。
もっとも、夫婦であっても、財産を一方から他方へ無償で移転すれば、原則として贈与税の対象になります。
夫婦だから自由に渡しても問題ないと考えるのは誤りです。
2 贈与税がかかる場合
贈与税は、贈与を受けた人(受贈者)に課税される税金です。
もっとも贈与があったからといって、すべてのケースで贈与税がかかるというわけではありません。
贈与税にも110万円の基礎控除というものがあり、その範囲内であれば課税対象になりません。
ただし、贈与額が110万円を超えた場合は、その超えた部分に課税されることになります。
贈与税の税率は、同じ金額であれば、相続税の税率よりも比較的高く設定される傾向にあります。
その他の贈与税と相続税の違いについては、こちらもご参照ください。
また、一般税率と特例税率があります。
特例税率とは、直系尊属(親や祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与に適用される税率です。
参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)
3 夫婦間でも例外的に贈与税がかからない場合はあるか
⑴ 基礎控除の範囲内である場合
贈与税にも110万円の基礎控除がありますので、その金額の範囲内であれば贈与税はかかりません。
この基礎控除は、贈与ごとではなく、1年間のトータルの枠で考えます。
具体的には、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産額が、110万円以内の場合には、贈与税はかからず申告も不要です。
また、この110万円の枠は、あげる人ごとではなくもらう人ごとで考えますので、贈与者の人数に関わらず、受贈者側の1年間の贈与額の合計で考えます。
他方で、贈与者は複数の人に贈与をすることができるので、年間110万円の枠に縛られることはありません。
具体的には、子供2人に各年間110万円ずつ贈与しても贈与税はかかりません。
⑵ 通常必要と認められる財産の贈与の場合
国税庁によると、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」には贈与税はかからないとされています。
「通常必要と認められるもの」とは何かというのが問題となりますが、日常生活に必要な生活費、学費、教材費や文具費といった教育費がこれにあたると解されています。
参考リンク:国税庁・贈与税がかからない場合
あまりに高額な物品を譲り渡す場合は、嗜好品として通常必要とは認められず、贈与と評価される可能性があるため注意した方がよいでしょう。
また、貯蓄目的で渡したお金は非課税になりません。
⑶ 居住用不動産の贈与の場合
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できるという特例が設けられています。
「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
この特例を利用するための主な条件は、以下となります。
- ①婚姻期間が20年以上であること
- ②居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金の贈与であること
- ③贈与の翌年の3月15日までに入居しており、その後も居住すること
- ④過去に同じ配偶者との間でこの特例を利用していないこと
この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の申告をする際は、以下の書類を添付する必要があります。
- ・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本
- ・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
- ・居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
参考リンク:国税庁・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
なお、不動産を夫婦間で贈与すると、贈与税が特例によりかからないとしても、登録免許税、不動産取得税といった税金がかかる可能性があるため注意が必要です。
また、夫婦間の贈与は必ずしも相続税の節税になるとは限りませんので、相続対策としての効果を期待しすぎないことも重要です。
なぜなら、配偶者には相続税について配偶者の税額軽減の特例(1億6,000万円 or 法定相続分まで相続税がかからない)があるからです。
登録免許税や不動産取得税、贈与をすると自宅の敷地について小規模宅地の特例の適用をすることができないことを考慮すると、生前贈与より、相続の方が有利なケースも多いので、節税目的で贈与を行う際には詳細なシミュレーションが必要となります。