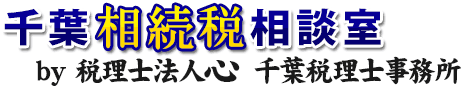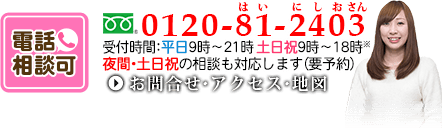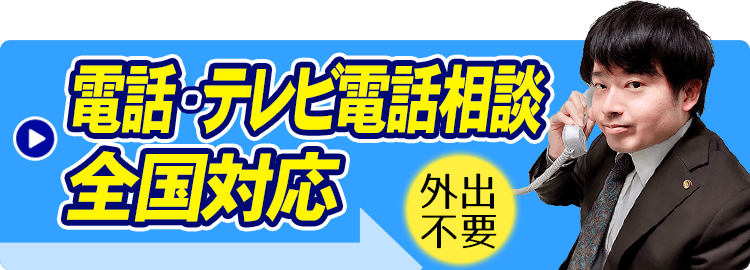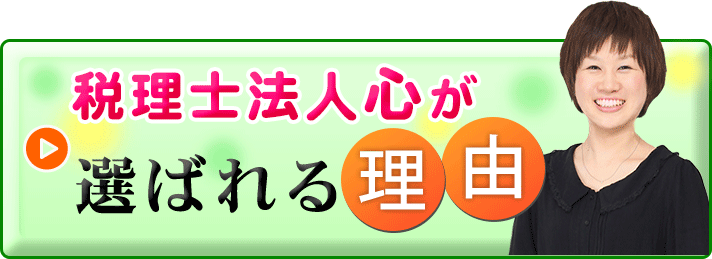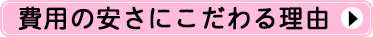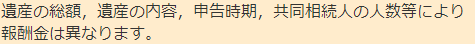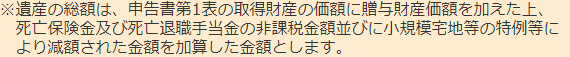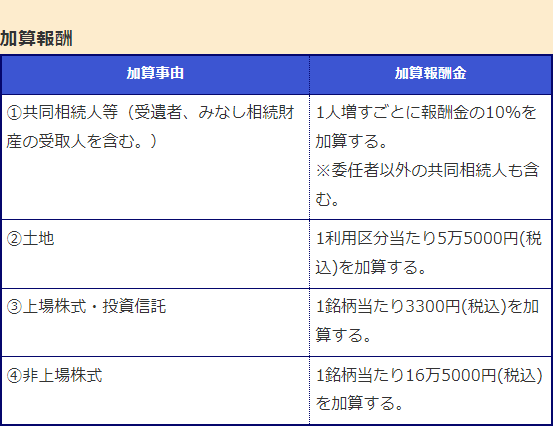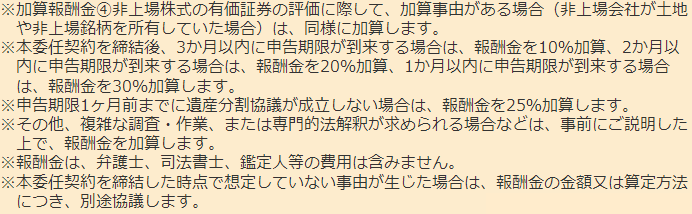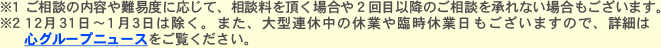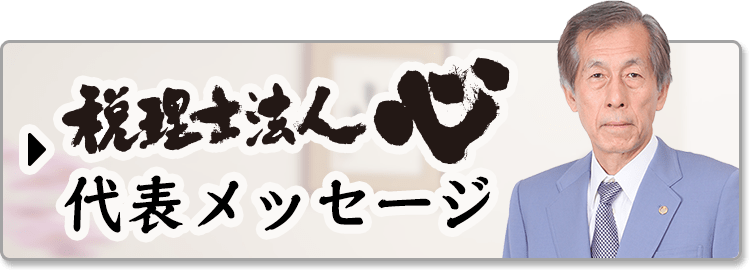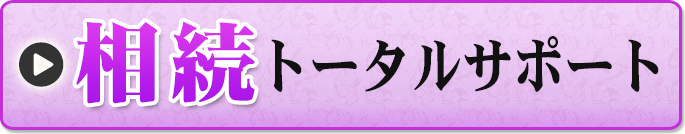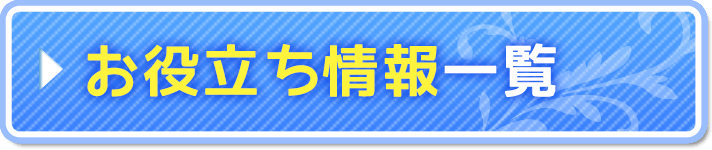お役立ち情報
相続税評価額の計算方法
1 相続税を計算するには相続財産の価値を調査することが必要
相続税の計算をするにあたっては、まず相続財産の総額を計算する必要があります。
相続税の課税対象となる相続財産には、土地や建物などの不動産、預貯金、上場株式、死亡保険金、退職手当金など様々なものがあります。
現金のように価値が明確なものばかりではないため、土地や建物などの不動産をはじめ、財産の種類ごとにそれぞれどのくらいの価値となるのかを評価しなければなりません。
相続財産の価値については、原則、相続開始日時点の時価を用いることとなりますが、相続財産の種類によって評価方法が異なる場合があります。
これらの相続財産は、相続税法や国税庁の通達に従って評価します。
参考リンク:国税庁・財産評価
以降で、財産の種類ごとに評価方法をご説明していきます。
2 土地の評価
⑴ 宅地の評価方法
宅地の評価方法には、大まかに分類すると、路線価方式と倍率方式があります。
市街地にある宅地は路線価方式、市街地から離れた宅地は倍率方式で評価されることが多いです。
ア 路線価方式
路線価は、毎年7月に国税庁が発表する路線価図で確認できます。
路線価の計算式は、「路線価 ×補正率・加算率 × 地積」です。
補正率・加算率を乗じることで、土地の形や使用条件などを踏まえた路線価の調整を行います。
具体的には、道路に対して土地の奥行が短すぎたり長すぎたりする場合、道路に接している間口が狭い場合、間口に比べて奥行が長すぎる場合、土地の形がいびつな場合などには、宅地の評価額が下がる可能性があります。
他方、対象の土地が2つ以上の道路に接している場合は、基本的に評価額が上がります。
イ 倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式です。
対象土地の固定資産税評価額に、地域ごとに定められた倍率を掛けて評価額を計算します。
倍率方式による計算式は、「固定資産税評価額 × 倍率」です。
⑵ 貸している土地や借地権の評価方法
ア 貸宅地
人に貸している土地を貸宅地といいます。
自分の土地を人に貸すと、その土地の所有者は利用が制限されますので、評価額は下がることになります。
貸宅地は、路線価や倍率により通常の評価をした後、借地権割合を控除します。
貸宅地を評価する際の計算式は、「自用地評価額×(1-借地権割合)」ですが、賃貸借契約の内容、賃料の金額によって、評価方法が異なるケースもあります。
イ 借地権
被相続人が土地を借りて家を建てていた場合、借地権も相続財産となります。
借地権の計算式は、「自用地評価額×借地権割合」です。
ウ 貸家建付地
自分の土地に賃貸アパートなどを建てて部屋を人に貸している場合、その自分の土地を貸家建付地といいます。
部屋を借りている人は直接土地を借りているわけではありませんが、建物を借りている人の権利が土地にも及ぶと考えて、計算します。
貸家建付地の計算式は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」です。
借家権割合は、一律30%(ごく一部の地域では40%)とされています。
賃貸割合は、賃貸中の部屋の床面積合計÷全ての部屋の床面積合計で計算します。
⑶ 土地の評価が難しい理由
不動産評価のルールの適用を難しくしている理由の一つとして、公法規制を参照しなければならないことが多いという点が挙げられます。
例えば市街化調整区域内の雑種地については、建物の建築が可能かどうかによって、評価額の減額割合が異なってきます。
そして、建物の建築が可能かどうかについては、都市計画法、条例、建築審査会基準を把握し、これを現地の状況にあてはめる必要があります。
3 建物の評価
⑴ 自宅の評価方法
固定資産税評価額がそのまま評価額となります。
マンションは専有部分の固定資産税評価額がそのまま評価額となります。
⑵ 貸家の評価方法
貸家は、30%の借家権割合を差し引いて評価します。
貸家の計算式は、「自用家屋の価額×(1-30%)」です。
⑶ 賃貸マンションの評価方法
賃貸マンションは、借家権割合と賃貸割合を差し引いて評価します。
賃貸マンションの計算式は、「自用家屋の価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」です。
⑷ 建築中の建物の評価方法
相続開始時に建物が建設中の場合は、相続開始時点で建築にかかった費用の70%が評価額となります。
⑸ 門、塀、庭園設備などの評価方法
原則として、調達価額を基準として、定率法による減価償却計算を行い、70%を乗じた金額が評価額となります。
4 預貯金の評価
預貯金については、相続開始日時点の残高が評価額となります。
定期預金については、預入残高に、相続開始日時点の源泉所得税額を引いた後の中途解約利息を加えます。
外貨預金については、相続開始日時点のTTB(対顧客電信買相場)により円換算した金額が評価額となります。
参考リンク:国税庁・外貨(現金)の邦貨換算
5 上場株式の評価
上場株式の場合は、価格が変動しますので、以下の4つの価格のうち一番低いものを評価額にできることになっています。
- ① 相続開始日の終値
- ② 相続開始月の毎日の終値の平均額
- ③ 相続開始月の前月の毎日の終値の平均額
- ④ 相続開始月の前々月の毎日の終値の平均額
参考リンク:国税庁・上場株式の評価
6 生命保険、死亡退職金の評価
生命保険の死亡保険金も、みなし相続財産として相続税がかかります。
死亡保険金には、受取人が相続人の場合、非課税枠が用意されています。
非課税枠の計算式は、「500万円×相続人の数」です。
なお、保険契約者は相続人であったとしても、被相続人が保険料を負担していた場合は、名義保険としてみなし相続財産に含めることになります。
死亡退職金も、生命保険の死亡保険金と同様に評価し、受取人が相続人であれば、「500万円×相続人の数」の非課税枠が利用できます。