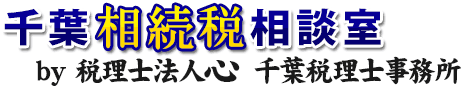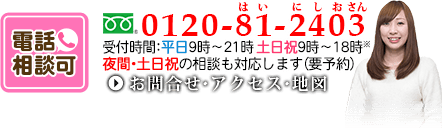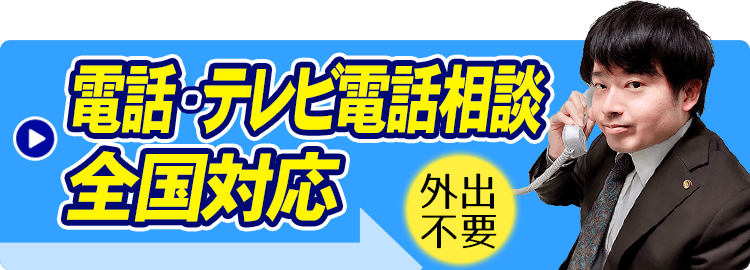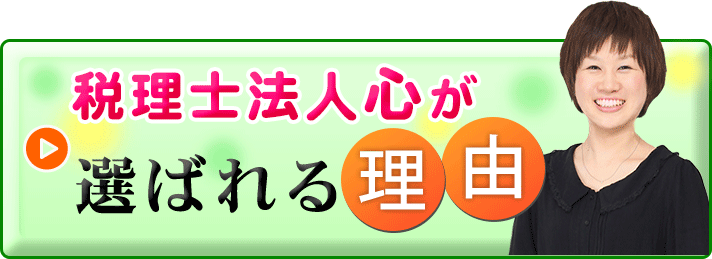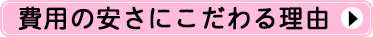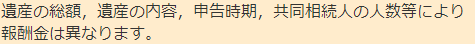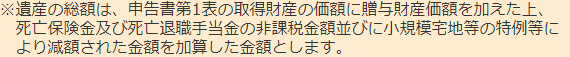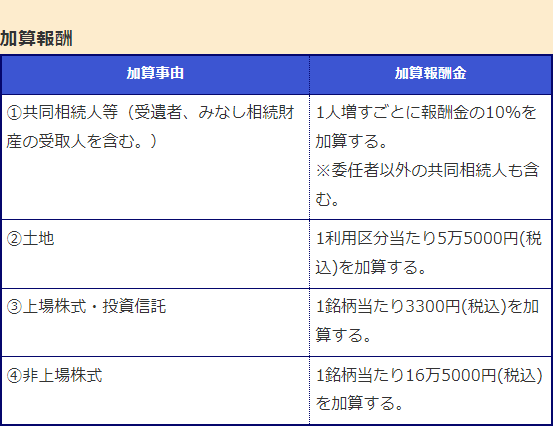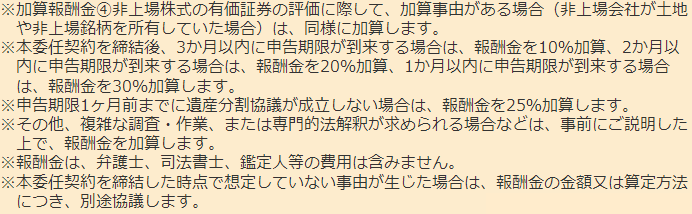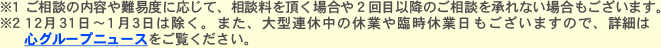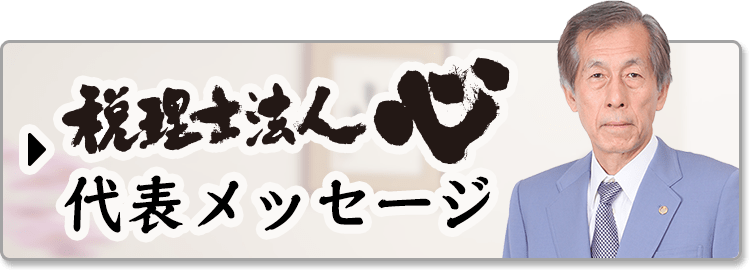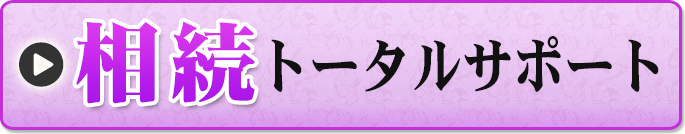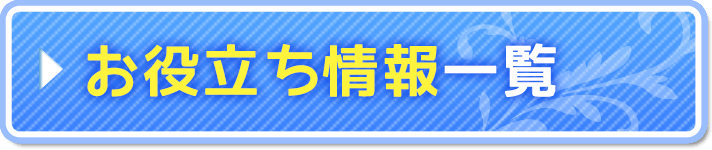お役立ち情報
相続税が払えない場合はどうすればよいか
1 相続税が支払えない場合はどのような場合か
相続税は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に支払う必要があります。
そもそも相続税は、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に支払うものであるため、一定の遺産があることが前提です。
この点、遺産に預貯金や現金が十分にある場合、それを相続することによって相続税を支払うことが可能です。
しかし、遺産として不動産だけを取得した場合には、預貯金や現金がなく、納税資金を確保できません。
また、申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は預貯金の解約ができず、遺産から相続税を支払うことができない上、税額を軽減する控除や特例なども使えないため、その分多く税金を払わなければならないことになります。
そのような場合、自分の手持ちの現金から相続税を支払うことになり、相続税が払えないということになってしまいます。
2 相続税が払えない場合、どうすればよいか
相続税の申告を行ったとしても、相続税を払わないと延滞税が課されてしまうため、なるべく早く払う必要があります。
その場合、金融機関などから借入をする、一部のみでも遺産分割協議を成立させて預貯金を解約し分配する、預貯金の仮払い制度を利用するといった方法があります。
あるいは、遺産を売却して現金化する、延納や物納の制度を利用するといった方法もあります。
3 預貯金の仮払い制度について
預貯金の仮払い制度とは、遺産分割協議が成立する前であっても一定金額までは相続人が被相続人名義の口座から払い戻しが受けられるという制度です。
この場合、金融機関ごとに、必要書類を提出することにより、死亡時の預貯金残高のうち法定相続分の3分の1か、150万円いずれか低い方の金額の払い戻しを受けることができます。
4 延納・物納
相続税額が10万円を超え、金銭で支払うことを困難とする事情がある場合には、申請により、担保を提供して分割払いが認められる場合があります。
ただし、手続きや細かい条件があるほか、延納の期間に応じて利子税がかかるため、支払う税金の総額は多くなってしまうので注意が必要です。
また延納によっても相続税が納められない場合は、物納という制度もあります。
しかし、物納に利用できる財産の優先順位が定められており、手続きが複雑であるため、使いやすい制度というわけではありません。
5 早めに納税資金への対策を検討しておく
以上からすると、相続税が払えずに困ることがないよう、早めに、できれば生前から対策を考えておくのがよいでしょう。
生前の相続税対策についても、税理士へご相談されることをおすすめいたします。
相続税申告をすると必ず税務調査が行われるのか 中央区で相続税の相談をお考えの方へ