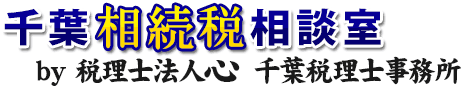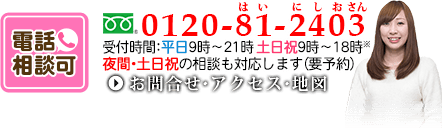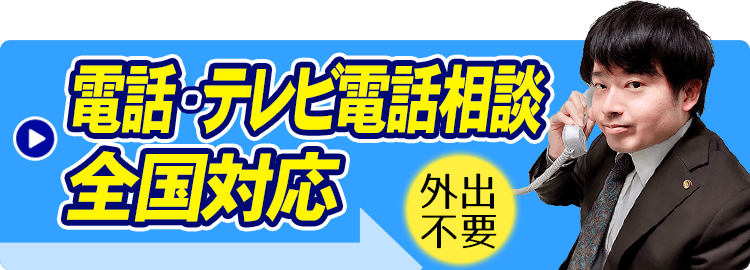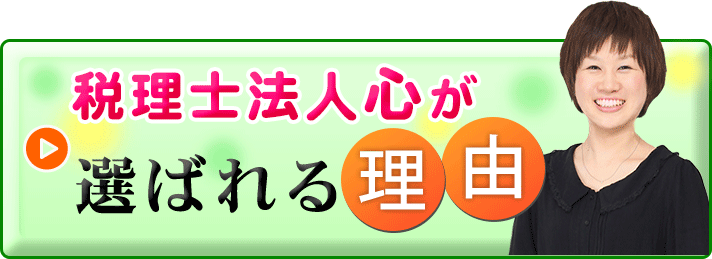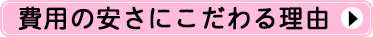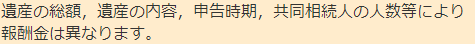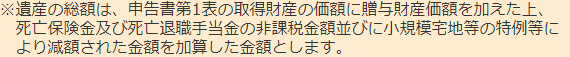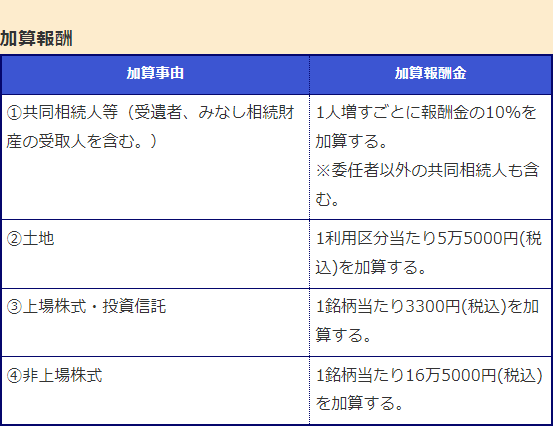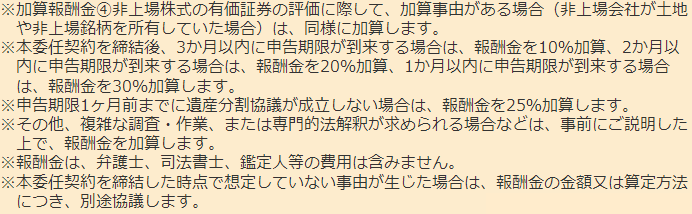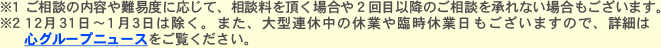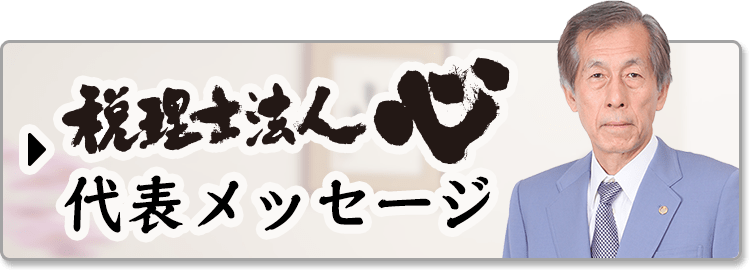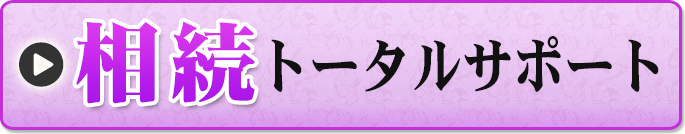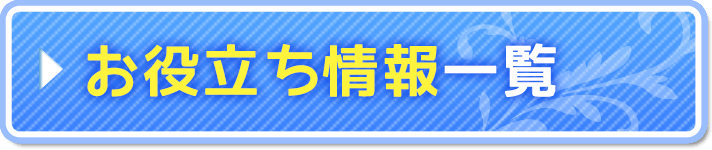お役立ち情報
相続税の申告の期限
1 相続発生から相続税申告までの手続きに関する期限について
相続が発生すると、葬儀を行い、相続財産を調査してその内容を把握し、自分が相続税を支払う必要があるかどうか確認するなど様々なことをしなければならず、その中には期限が決められているものが多くあります。
特に、相続税の申告については、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月が期限になります。
相続税申告を行う前に済ませておかなければならない手続きもあり、それらの手続きについて相続が発生してから慌てて確認すると、誤った対応をしてしまう危険性がありますので、お早めに確認しておくことをおすすめします。
2 相続税申告に関わる各手続きの流れや期限
⑴ 被相続人の死亡(相続発生)
⑵ 遺言書を探す、検認手続き(自筆証書遺言の場合)
遺言書があるかどうかによって、その後の手続が全く変わってきます。
遺言書がある場合は、原則として、遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
遺言書がない場合は、全ての相続人間で遺産分割協議をして遺産を分けることになります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、自宅の金庫、タンスや銀行の貸金庫にある場合が多いと思われます。
公正証書遺言は、相続発生後、全国の公証役場で検索ができます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せずに、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において、検認手続をする必要があります。
⑶ 相続人調査
遺産分割協議をするにあたって、相続人を確定する必要がありますので、相続人調査をしなければなりません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等を集めていく作業が必要になります。
⑷ 相続財産調査
遺産分割協議をするにあたって、どのような遺産があるかを確定する必要がありますので、相続財産調査をしなければなりません。
主な相続財産としては、不動産、預貯金、現金、株式等の有価証券等が挙げられます。
⑸ 相続税の申告、納税(相続開始後10か月)
遺産の金額によって相続税が発生する場合があります。
相続税には基礎控除が定められているので、相続財産が基礎控除の額の範囲内であれば、相続税申告が不要ですし、相続税を支払う必要はありません。
他方、基礎控除額を超える遺産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の申告と納税には、相続開始10か月以内という期限があります。
申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけない点に注意が必要です。
⑹ 相続税の税額軽減措置の適用(相続税申告期限後3年)
相続税には、様々な税額軽減措置が設けられています。
具体的には、配偶者の税額軽減といって、配偶者であれば法定相続分または1億6千万円までの相続分に対しては相続税がかかりません。
また、遺産の中に宅地がある場合には、小規模宅地の特例が利用できる場合があり、土地の評価額を最大80%軽減できる場合があります。
ただし、これらの相続税軽減を受けるためには期限があります。
遺産分割協議がまとまらない場合であっても、相続税の申告期限内である相続開始から10か月以内に、未分割として相続税の申告をする必要があります。
そして、この申告をする際、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を作成し、相続税申告書に添付して税務署に提出します。
申告期限後3年以内の分割見込書とは、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議ができる見込みがあるという内容の書面です。
この書面を提出した後、3年以内に遺産分割協議がまとまった場合は、遺産分割協議終了後4か月以内に税務署に対して、更正請求をすることによって、相続税の軽減措置を受けることができます。
例外的に、遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請を行い、この申請が税務署長によって認められた場合には、3年が経過した後であっても、相続税の軽減措置を受けることができます。
ただし、この申請が認められるのは、遺産分割調停等、遺産分割の解決に向けた何らかの法的手続がとられている場合に限られます。