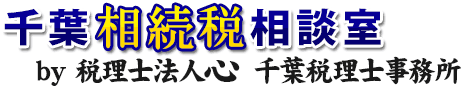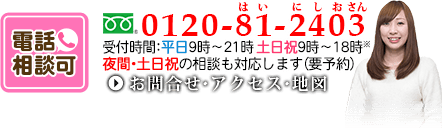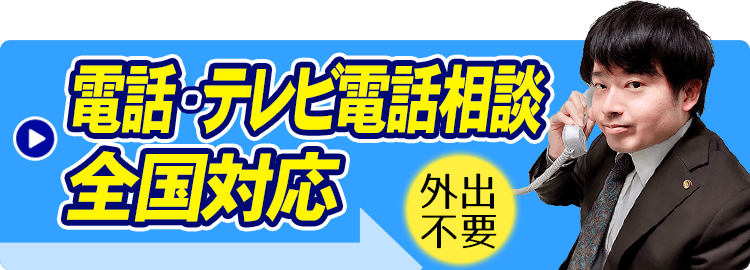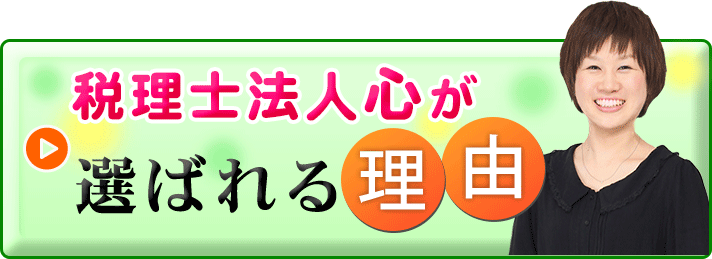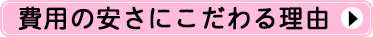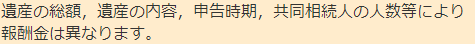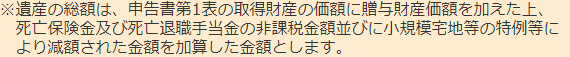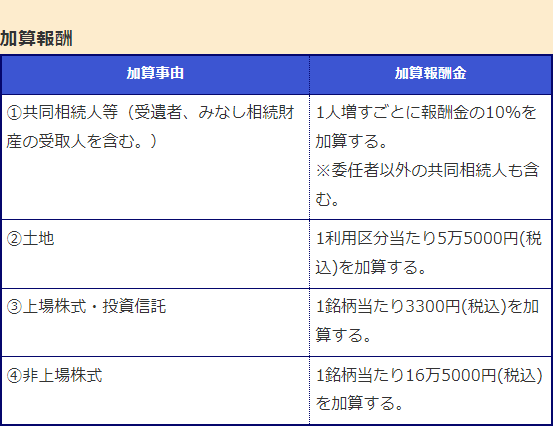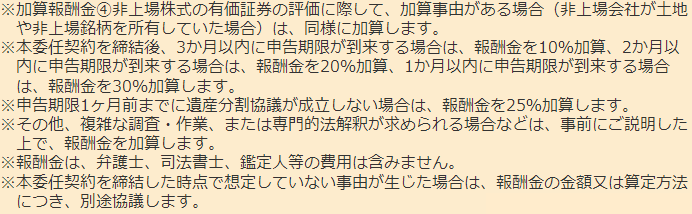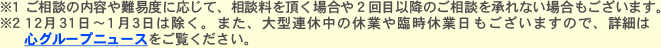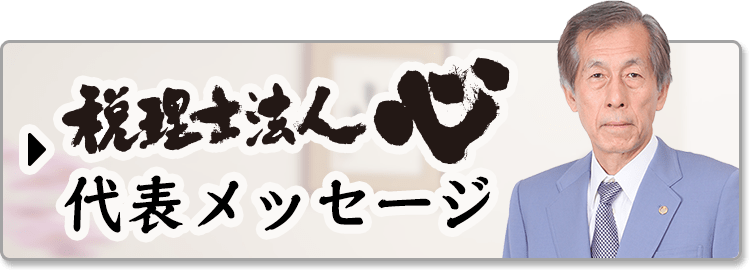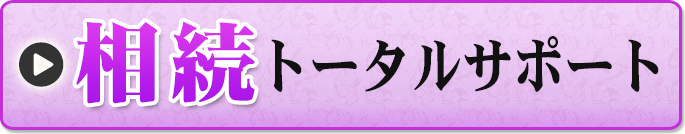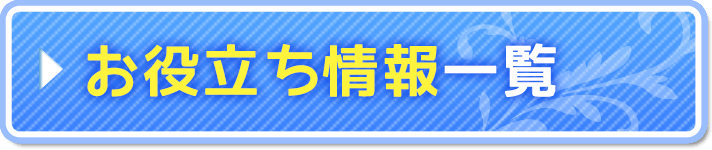お役立ち情報
相続税の申告に必要な書類
1 相続税の申告に必要な書類はどのようなものがあるか
相続税申告をするにあたって、必要な書類はたくさんあります。
個々のご事情によって、必要となる書類は様々ですが、各自それらの書類を不備なく、適切に収集しなければなりません。
国税庁のホームページには、相続税の申告書等の様式一覧をまとめたページがあります。
参考リンク:国税庁・相続税の申告手続
ご覧いただくと分かるとおり、各ケースによって必要な書類が異なりますし、その量は膨大なものです。
大まかには、①相続税申告書関係、②相続人関係、③相続財産関係、④債務・葬式費用に関するものに分けられると思います。
以下、基本的なものに絞って、ご説明いたします。
2 ①相続税申告書関係
⑴ 相続税申告書
一番重要なのは、もちろん相続税申告書です。
ご自身で作成する場合は手書きで作成される方もいらっしゃるかもしれませんが、税理士に依頼する場合、専門のソフトを使用して作成します。
また、税理士に依頼する場合は、税務代理権限証書も提出します。
相続税申告書は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。
⑵ 贈与契約書等の有無の確認
生前贈与を受けていた方は、贈与契約書等の有無を確認します。
被相続人から過去3年以内(令和6年1月1日以降の贈与から、3年の期間を段階的に7年に延長)に贈与を受けていた方や、相続時精算課税制度の適用を受けている方は、相続税申告書作成のための確認資料として、贈与契約書や贈与税申告書の控えを保管しているかどうかご確認ください。
⑶ 過去の相続関係の確認
被相続人が自身の亡くなる前10年以内に、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額が控除される可能性があります。
この制度を相次相続控除といい、この制度を利用できるかどうかを確認するためには、被相続人が亡くなる前10年以内の相続税申告書の控えをご確認ください。
参考リンク:国税庁・相次相続控除
3 ②相続人関係
被相続人の戸籍や相続人が何人いるか特定するための書類が必要です。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本、遺言書又は遺産分割協議書の写し、遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書、相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写しなどが必要です。
4 ③相続財産関係
課税対象となる相続財産の特定と評価のための資料が必要になります。
被相続人が保管している場合もありますが、被相続人の財産が全く分からない場合もありますので、その場合は相続財産調査が必要です。
相続税の課税対象となる財産については、こちらをご参照ください。
⑴ 不動産関係
不動産の所有権や、賃貸借関係を証明する資料が必要になります。
具体的には、名寄帳または納税通知書の課税明細書、固定資産税評価明細書、登記事項証明書が必要になります。
また、賃貸している不動産がある場合は、不動産賃貸借契約書が必要です。
他人の農地を小作している場合は、農業委員会の耕作証明書が必要です。
その他のケースによっては、土地の賃貸借に関する書類が必要になる場合があります。
⑵ 預貯金関係
預貯金については、相続開始日時点の被相続人名義の預貯金残高を確認する必要がありますので、各金融機関の残高証明書が必要です。
また、信用金庫や協同組合に被相続人名義の口座がある場合は、出資金の有無も記載した残高証明書を取得するとよいでしょう。
定期預金がある場合は、相続開始日時点における未収の預金受取利息額を確認する必要がありますので、定期預金の利息計算書が必要です。
また、過去に多額の入出金や贈与がないかを確認するために過去5年分の通帳を確認させていただくことが多いです。
⑶ 上場株式、投資信託等の金融商品関係
証券会社から、被相続人の死亡日現在の預り証明書や登録証明書を取得する必要があります。
また、上場株式について、相続開始後に配当がある場合は、配当金の支払通知書が必要になります。
また、過去に多額の入出金や贈与がないかを確認するために、被相続人の相続開始前3年間の取引明細書を確認させていただくことが多いです。
⑷ 生命保険関係
死亡保険金もみなし相続財産として相続税の課税対象となりますので、資料が必要になります。
具体的には、保険金の支払通知書、生命保険証書や解約返戻金の額が分かる書類が必要になります。
⑸ その他の財産関係
被相続人がゴルフ会員権やリゾート会員権をお持ちの場合もあると思われます。
その場合は、預託金証書または証券のコピーが必要です。
また、相続人が地金・宝飾品等の貴金属、書画・骨董等で金銭的価値があるものをお持ちの場合は、鑑定書をご用意いただくか、購入年月日・購入金額・購入先が確認できるものをご準備ください。
5 ④債務・葬式費用に関するもの
⑴ 債務について
被相続人に借金がある場合は、借入残高証明書や金銭消費貸借書が必要です。
また、相続開始前に発生した被相続人が支払うべき費用について、相続開始後に支払った場合は、その費用分を債務として扱うことができますので、相続財産から控除できることになっています。
具体的には、住民税、固定資産税、事業税、国民年金や国民健康保険料、介護保険料などがあります。
提出すべき資料としては、納税通知書等、支払ったことが分かる書類が必要です。
⑵ 葬式費用について
葬儀関係の費用についても、相続財産から控除できるものがあります。
具体的には、通夜・葬儀に関する費用、食事代、お布施、心づけ等があります。
提出すべき資料としては、葬儀関係費用の領収書、心づけ等の領収書またはメモが必要です。
参考リンク:国税庁・相続財産から控除できる葬式費用
6 税理士にご相談ください
以上のとおり、相続税申告の際には、様々な書類を準備する必要があります。
基本的な書類だけでも、かなりの量になりますので、申告期限に間に合わせるためには早めの準備が重要になってきます。
いざ自分が相続税申告をする必要がある場合に、どのように手続きをすればよいか分からない方や、申告に必要な書類が何かを知りたいという方も多いのではないでしょうか。
まずは相続税を多く取り扱っている税理士に相談して、何から準備すればよいか確認されることをおすすめします。
当法人には相続税申告を得意とする税理士がおりますので、お気軽にご相談ください。