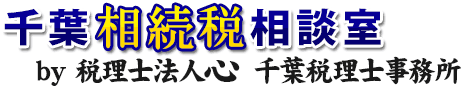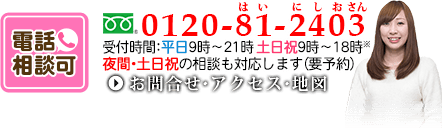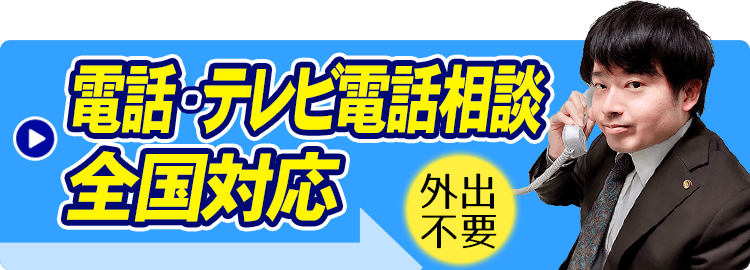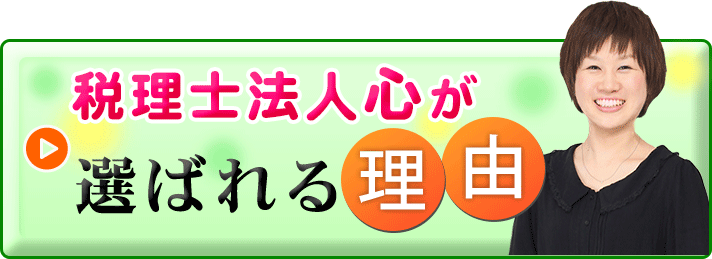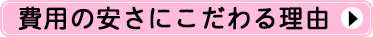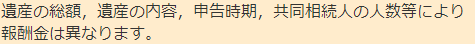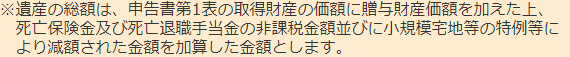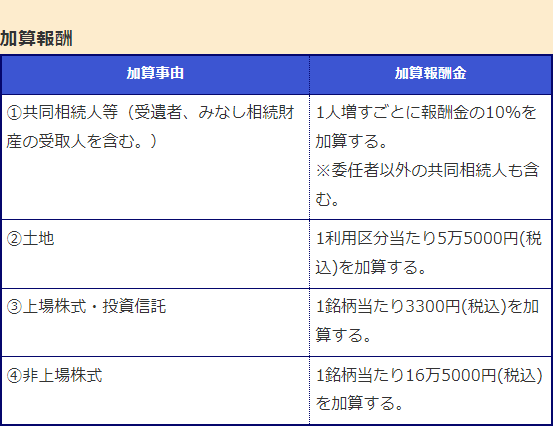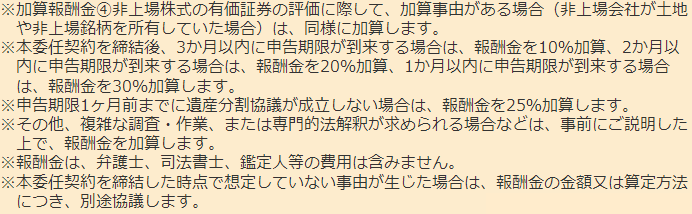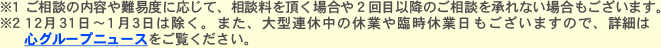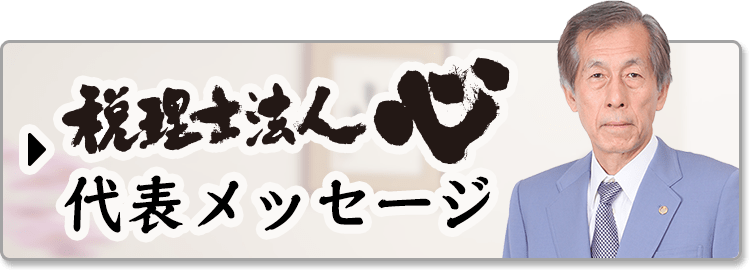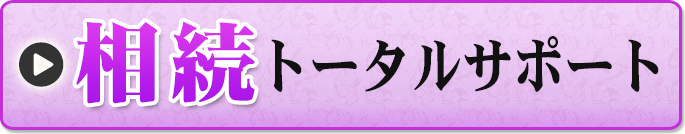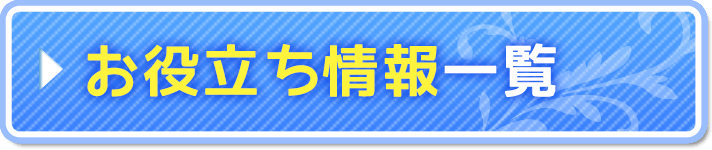お役立ち情報
相続税申告の失敗事例
1 相続税申告前の調査不足により税務調査で名義預金が発見された事例
被相続人が亡くなり、被相続人の家族は遺産の調査をしたところ、基礎控除の範囲を超える相続財産があったため、相続税の申告と納税を行いました。
しかし、後日、税務署から連絡があり、追加で相続税を支払うよう求められました。
税務署によると、税務調査の結果、申告されていない銀行に多額の預貯金があることが分かったが、申告されていないとのことでした。
このようなケースだと、財産を少ないと見積もって申告したことになるため、「過少申告加算税」が課されてしまいます。
過少申告加算税の税額は、増えた分の差額×10%という計算式で求められます。
ただし、増えた分の差税額のうち、当初に申告した税金または50万円のうち大きい方の金額を超過する部分があるときには、その税率が15%になります。
2 相続税対策で不動産を買ったが結果的に負動産となってしまった事例
被相続人は、生前、多額の預貯金を持っていたため、このまま相続が発生すると多額の相続税の支払いが予想されました。
そこで、相続税対策として、数億円の費用をかけて、土地の購入とアパートの建築を行うことにしました。
預貯金を不動産に変えた方が預貯金をそのまま持っておくよりも相続税の負担を軽減できる場合があるため、この方法が必ずしも間違っているわけではありません。
適切に不動産を活用できれば、相続税対策として有効になり得ます。
しかし、相続税対策でアパートを建築したとしても、立地が良くなかったり、タイミングが悪く、同時期に近場に同じようなアパートが建設されたような場合は、借り主が現れず空室となってしまうため、十分な家賃を回収できず、結果的にアパートがマイナスの不動産となってしまいました。
このような事態を避けるために、不動産を購入する際は慎重に調査等をする必要があります。
3 一次相続の際に二次相続を考えずに遺産分割をしてしまった事例
一次相続で父が亡くなり、相続人として母、長男、二男がいました。
父の遺産は、全部で1億円ありましたが、遺産分割協議の結果、母が全遺産を相続しました。
この時は、配偶者である母が遺産を相続し配偶者控除特例を利用したため、相続税は0円で済みましたが、母は、その1年後に病気で亡くなってしまいました。
その結果、長男と二男は、母が相続した1億円と、もともと母が所有していた4000万円を合わせた、1億4000万円を相続することになりました。
相続税は、遺産額が高ければ高いほど、また相続人の人数が少なければ少ないほど、負担が重くなるという性質があるため、長男と二男は、とても重い相続税を支払うことになりました。
このように一次相続では相続税の負担を軽減できても、二次相続でかえって多くの税金を支払うことになるケースもあるため、一次相続の段階で、将来の二次相続のことも考えて遺産分割をする必要があります。
4 当初の遺産分割協議書の内容と異なる分割をしてしまった事例
被相続人が亡くなり、相続人である配偶者と子1人で、被相続人が持っていた収益物件について遺産分割協議を行い、配偶者がこの収益物件を取得することで遺産分割協議書を作成しました。
その後間もなく、子が経済的な理由でお金が必要になったことから、この収益物件の持分の半分を子が相続するように遺産分割協議をやり直しました。
そうしたところ、配偶者から子への収益物件の持分の変更について、税務署から贈与であると指摘を受け、贈与税が発生することとなりました。
このような事態を避けるために、遺産分割協議書作成後のやり直しには注意が必要です。