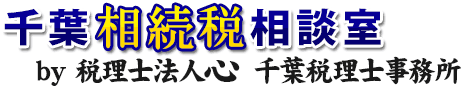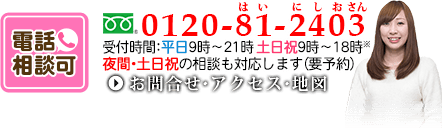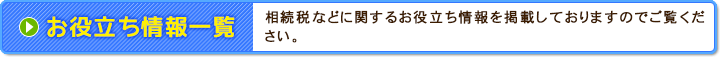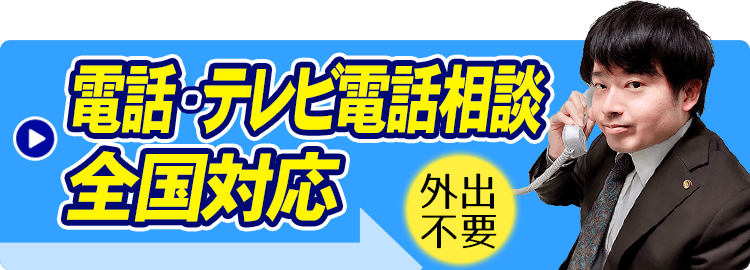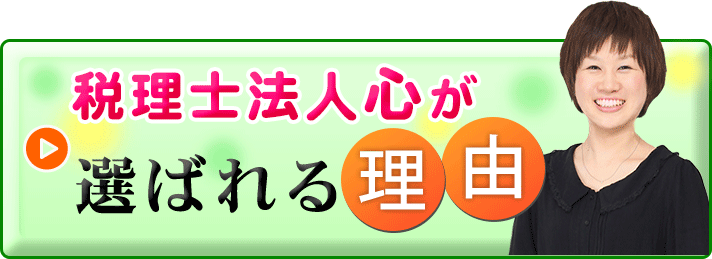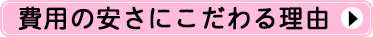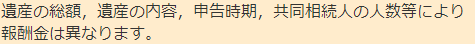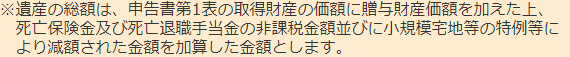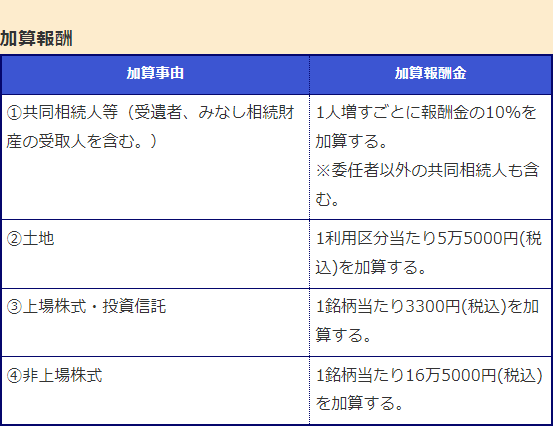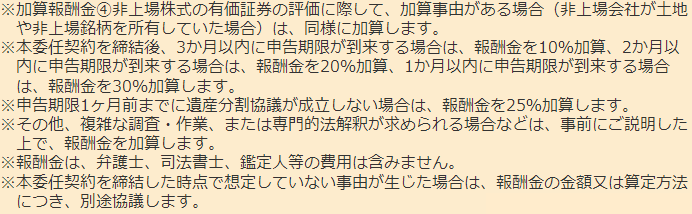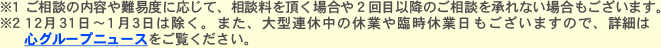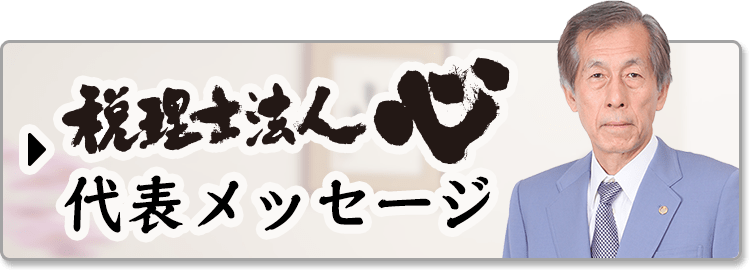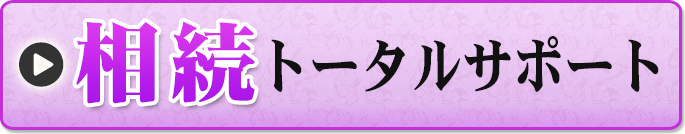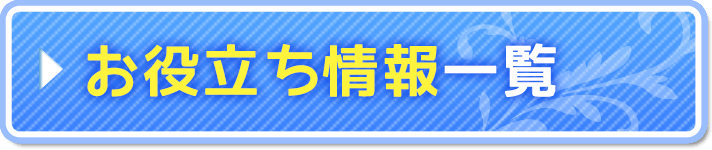生命保険で相続税対策をする場合のQ&A
生命保険には相続税の非課税枠があると聞いたのですが、本当ですか?
死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、被相続人が被保険者で保険料を負担し、相続人が受取人となる生命保険の場合、全ての相続人の受け取った保険金が合計して「500万円×法定相続人の数」の金額までであれば、非課税となります。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金
非課税枠を利用する際には、どのような注意が必要ですか?
相続を放棄した人や、廃除や欠格などにより相続権を失った人には適用できません。
また、被相続人に養子がいる場合、この非課税枠を適用できる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。
参考リンク:国税庁・相続人の中に養子がいるとき
生命保険は、遺産分割対策としてどのように活用できますか?
死亡保険金は、受取人固有の財産となり、原則として遺産分割の対象外であるため、生命保険を活用することによって確実に一定の財産を取得させることができます。
また、受け取った死亡保険金を活用して代償金を支払うことができ、スムーズに遺産分割を行うことができるようになります。
納税資金として死亡保険金をどのように活用できますか?
相続税の申告が必要な場合には、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税を納付しなければなりません。
相続財産のほとんどが自宅などの不動産であり、現金や預金がないような場合、死亡保険金を納税資金として確保しておくことで、相続財産の売却等をしなくて済みます。
死亡保険金の受取人は誰にするのがよいのでしょうか?
保険金の受取人を配偶者としている場合、配偶者は元々税額軽減により納税額が発生しないケースも多く、配偶者が子の負担する相続税を納めると贈与となってしまいかねません。
また、配偶者が保険金を受け取ることにより、結果的に、二次相続の際に子が負担する相続税が高くなる可能性があります。
そのため、配偶者の生活保障を特に考えなくてもよい場合には、配偶者以外の子を受取人にしておくとよいでしょう。
このように、二次相続まで考慮したうえで、死亡保険金でいくら確保するのか、受取人を誰にするかなどを検討しておくことが必要です。
税理士によって相続税額が違うことについてのQ&A ビットコインなどの仮想通貨と相続税に関するQ&A