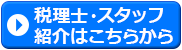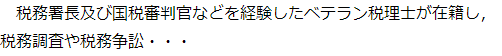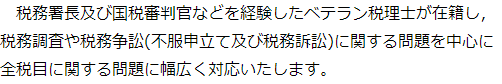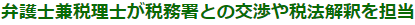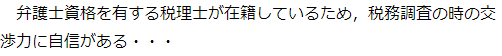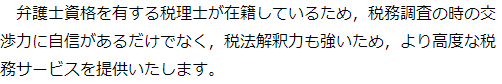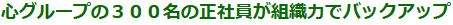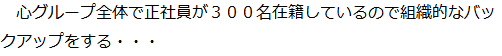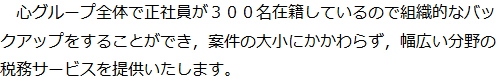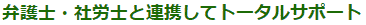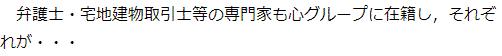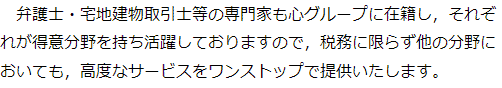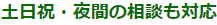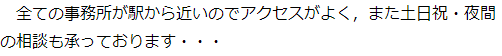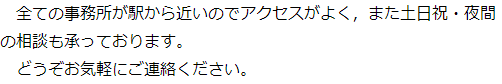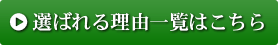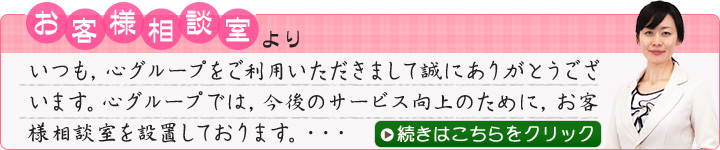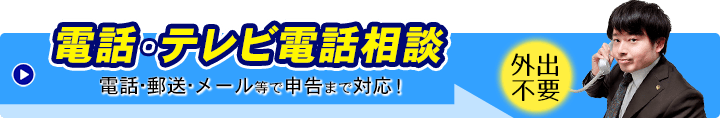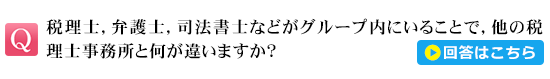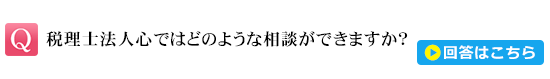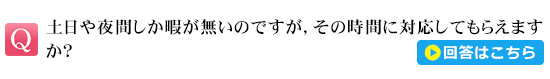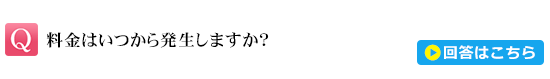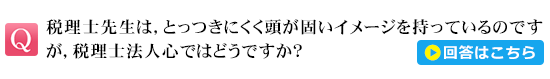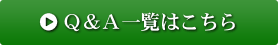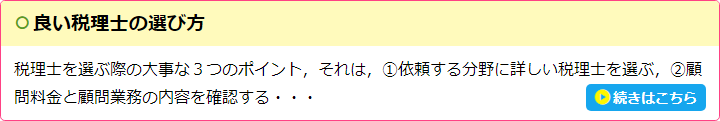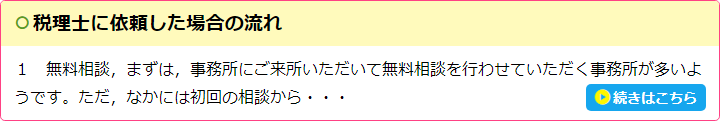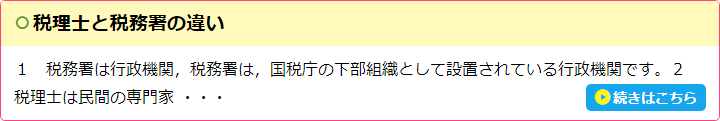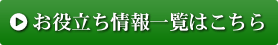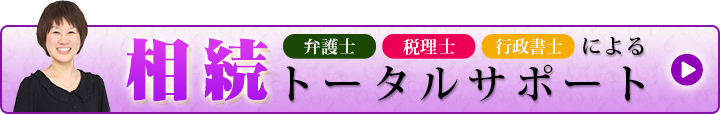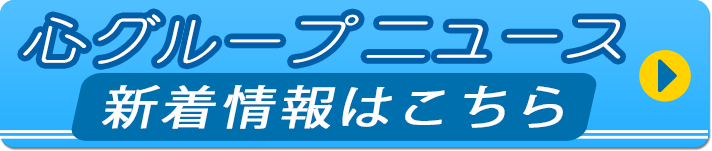千葉の方もご利用ください
当法人の事務所は駅から近い場所にあります。お車でお越しの際には、事務所の周辺にある駐車場を利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
税理士に依頼できること
1 税理士と業務内容

税理士は、税務に関する専門家であり、個人や法人の税務手続きや税務相談、税務調査対応など、さまざまな税務サービスを提供しています。
税理士に依頼できることは多くありますので、以下では主な業務内容と、その詳細について説明します。
2 申告書の作成と提出
税理士が一般的に依頼される業務は、所得税、法人税、消費税、相続税などの申告書の作成と提出です。
申告書は、税法に基づいて正確に作成しなければなりません。
特に、法人税や相続税の申告は複雑です。
税理士は、納税者の事業の財務状況や収入、個人資産の状況に基づいて、適切な税額を計算し、申告書を作成します。
また、申告期限内に税務署に提出する手続きも代わりに行います。
3 税理士と相続税対策
相続税は、財産を相続した際に発生する税金ですが、適切な対策を講じることで税額を減らすことが可能です。
このように税理士は、相続税の計算だけでなく、相続税額を減額させるための遺産分割のアドバイスや、節税対策の提案も行います。
例えば、生前贈与、養子縁組、生命保険の活用など、相続税を減額するための具体的なプランを提供します。
また、相続税申告書の作成・提出を代わりに行います。
4 税理士と税務調査対応
税務署からの税務調査が入ると、過去の申告内容に誤りがないか、調査が行われます。
税務調査は一般的に数日間にわたって行われ、調査結果によっては追加の納税が求められることがあります。
税理士は、税務調査の際に立ち会い、納税者の代理として税務署と交渉を行います。
また、調査の準備や調査後の対応、修正申告が必要な場合の手続きもサポートします。
5 年末調整・給与計算の代行
企業にとって、従業員の給与計算や年末調整は重要な業務です。
しかし、これらの業務は煩雑であり、法律や税制の知識が必要なのはもちろん、これらは毎年のように変わりますので最新の情報も把握しておく必要があります。
税理士は、企業の給与計算や年末調整を代理で行い、適切な税額を控除したり社会保険料を計算したりします。
また、源泉徴収票や給与明細の作成もサポートし、従業員への説明や税務署への提出書類の準備も行います。
6 税理士と記帳代行と会計帳簿の作成
中小企業や個人事業主にとって、日々の取引を正確に記録し、会計帳簿を作成することは欠かせません。
しかし、これらの作業は時間がかかり、専門知識が必要です。
税理士は、納税者の代わりに記帳代行を行い、月次や年次の帳簿を作成します。
これにより、企業や個人事業主は本業に専念でき、財務管理も適切に行われるようになります。
税理士を選ぶ際のポイント
1 相談したい税目に詳しいか確認してみる

相続税申告の依頼を考えている場合は、相続税(資産税)に関する申告の経験の多い税理士に依頼をすることをおすすめします。
税理士の業務は、相続税等の資産税だけではなく、法人税や所得税、顧問業務など、多岐にわたります。
それぞれの税目によって税体系が異なりますので、普段は法人の顧問や決算業務を中心に対応している税理士ですと、相続税等の資産税には精通していないというケースもままあります。
そのため、税理士に相談する際は、相談したい税目に詳しい税理士であるかを確認することが大切です。
普段からお願いしている税理士がいる場合であっても、相続税申告については相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
相談の際、相続人や相続財産について情報を伝えた上で、税理士の意見やアドバイスを聞いてみると、その税理士が相続税に詳しいかどうか、ある程度は分かるかと思います。
相続税を日々取り扱っている税理士であれば、スムーズに試算をした上で、特例の適用等について重要な箇所について、詳しく聴き取りが行われるはずだと考えられるためです。
2 料金について
税理士選びのもう1つのポイントは、料金です。
税理士の報酬は自由化されています。
特に相続税の分野においては、高い税理士事務所と安い税理士事務所で、同じ申告内容でも2倍以上の費用の差があることも珍しくありません。
高いからサービスが良い、安いからサービスが悪いとは限りません。
相談の質と値段とのバランスをよく考えて、ご依頼先を決めるのがおすすめです。
税理士費用は、基本報酬金、加算報酬金、特急料金等、積み上げ方式になっています。
そのため、費用が高くなるほど、サービスの範囲も広がることが多いです。
とはいっても実際は事務所によって様々ですので、費用をよく確認した上で比較することをおすすめします。
3 適切なコミュニケーションができるかどうか
税理士に依頼してから、実際に申告に進むまでの間には、税理士との間で何度かやり取りをすることになります。
不明な点や不安が残ったまま申告・納税することにならないよう、気軽に質問を投げかけられるかどうか、それに対して適切に回答してもらえるかどうかなど、コミュニケーションがスムーズに行えるかどうかという点についても、税理士を選ぶ際の重要なポイントといえます。
また、税務顧問や年次の決算申告を依頼する際にも、税理士との定期的なコミュニケーションが必要となります。
この場合でも、質問のしやすさ、回答の適切さなどは重要なポイントになるといえます。
依頼してから後悔しないために、コミュニケーションが適切にとれるか、自分との相性が良さそうかは、初めの相談の際にしっかりと確認するのがおすすめです。
税理士に相談すべき場合はどのようなときか
1 会社員で税理士に相談すべき場合

会社員が副業をしている場合や株式投資をしている場合、不動産の賃貸収入など収入源が複数ある場合は、確定申告が必要となるなど、税務上の取扱いが複雑になる可能性があります。
税理士には、これらの所得について適切な税金の計算や申告方法、節税の方法などのアドバイスを求めることができますし、申告を依頼することができます。
他にも、住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税の限度額といった控除を申告する場合には、税理士に相談することで節税のポイントについてアドバイスを求めることができます。
また、会社員が退職や転職をする場合にも税務上の取扱いが変わることもありますので、そういったタイミングも税理士に相談すべきといえます。
2 個人事業主で税理士に相談すべき場合
個人事業主の場合、事業を開始する際に税務署に届け出をしたり、日々の記帳方法や経理システムの導入等、経理・会計処理を初期の段階から適切に行っていく必要があります。
そのため、事業を開始する前に、税理士へ税金関係の全般的な相談をしておくことがおすすめです。
また、事業の収入が増えていくにしたがって税務上のリスクも高まり、税務調査のリスクも増えていきます。
特に、収入が1000万円を超えると2年後から消費税の課税事業者になり、税務処理が複雑化し、納めるべき税額も増える傾向になります。
そのため、事業収入が増え、安定してきたタイミングも税理士に相談すべきといえます。
3 法人で税理士に相談すべきケース
法人の場合、設立の際には税務署、県税事務所、法務局といった様々な機関に届け出をしなければなりません。
法人設立の届け出とあわせて、青色申告の申請書など税金に関する書類も必要に応じて提出する必要があります。
また、開業費の範囲等の知識も知らなければ、法人設立の際から税金を余分に支払うことになってしまうおそれもあります。
そのため、法人設立の前に、じっくりと税理士に相談しておくことが、事業をスムーズに開始したり余分な税金の支払いを避けたりするために必要なことといえます。
また、事業拡大をして収入が増えると、個人事業主と同じように、消費税の課税事業者になり、税務処理が複雑になりますし、そもそも法人税の申告は所得税の申告よりも作成する書類も多く、その内容も複雑です。
そのため、決算を終えて申告が必要なとき、事業拡大をしていくときなども税理士に相談するとよいといえます。
税理士に相談する際に気を付けること
1 税理士を探す際の注意点

税理士を探すには、インターネット検索、人からの紹介、紹介会社を利用する、街中の看板や広告から探す等、様々な方法があります。
この中でも、人からの紹介の場合は紹介者を一度通しているため、一定の信頼性があります。
ただし、紹介してくれた人にとってはいい税理士でも、紹介を受けた人にとっては相性が悪かったり、求めていることが違ったりする場合もあります。
インターネット検索で探す場合には、事前にその税理士の得意分野を確認することができますし、ホームページで報酬体系を確認することができるというメリットもあります。
とはいえ、どの方法で税理士を探すとしても、一度会ってどのような人柄かを確認してみることは重要です。
2 税理士の注力分野に注目する
すべての税理士が、すべての税目についての知識、経験を有しているわけではありません。
税理士試験においては、すべての税目について合格しなくとも、税理士資格を取ることが可能です。
一部、必須の科目はありますが、いくつかの科目は選択制となっており、例えば実務で計算を求められることのない住民税であっても、試験にさえ合格すれば、所得税、法人税、相続税といった実務でよく使う税目について合格したのと同じ扱いを受けます。
また、全国の税理士の数と年間の相続税申告数を単純に割り算すると、税理士一人あたり年間で2件申告できるかどうかという程度になり、十分な実務経験を積むことが難しい状態です。
さらに、すべての税理士が等しく申告を行っているわけではなく、一部の税理士に依頼が集中しているため、相続税申告を特化して業務している税理士と、普通の税理士には大きな差があるといえます。
3 税理士に相談するタイミングにも注意する
税理士に相談するタイミングは、税目によって異なります。
例えば、所得税の申告については、毎年3月15日までに申告する必要がありますが、年明けくらいの時期から、税理士は申告準備のため忙しい時期に入ります。
したがって、そのタイミングで税理士に依頼しようとしても断られてしまうことがあります。
そのため、できれば年内のうちにまずは相談されることをおすすめします。
また、相続税申告は、相続開始を知ってから10か月以内に申告する必要があります。
相続税申告の場合も、申告期限の1~2か月前に税理士に相談しても断られる可能性がありますし、受けてもらえたとしても、特急料金というような形で税理士報酬が割高になることが多いです。
そのため、相続が開始し、49日が過ぎた頃には一度税理士に相談することをおすすめします。
税理士に相談する際に必要なこと
1 所得税・法人税のご相談の場合

⑴ 自社の業務内容を簡潔に説明する
税理士に相談する際、まずは、小売業、卸業、不動産業、運送業、医療関連業など、ご自身がどのような業務を行われているのか、簡潔にご説明いただければと思います。
一般的によく税理士に依頼される事業であれば、概ね、税理士の方でお話を伺いながら費用感の目安を想定できるからです。
⑵ 年間の売上が分かる資料を用意する
売上規模によって、仕訳の入力数が異なりますので、年間の概ねの売上規模が分かる資料をご用意ください。
資料が準備できなくても、口頭で説明していただければそれで問題ない事務所が多いかと思います。
⑶ 月間の経費が分かる資料を用意する
経費の量によって、仕訳数が全く異なりますので、月間の経費が分かる資料もご用意いただければと思います。
また、経費を自社で入力するのか、それとも領収書等を税理士に送付し記帳代行から依頼するのか、それによっても税理士報酬が異なります。
そのため、どちらを希望されるか、つまり、どこから税理士に依頼するのかもあらかじめご検討いただくとスムーズです。
⑷ 昨年までの決算・申告資料を用意する
昨年までの申告資料を拝見すれば、白色申告・青色申告の区別もつきますし、消費税に関して課税事業者なのか、免税事業者なのかの区別もつきますので、正確なお見積もりをすることができるようになります。
また、決算資料を見れば、仕訳数等の分量が分かりますので、こちらも正確なお見積もりをするためにはご用意いただいた方が望ましいといえます。
2 相続税のご相談の場合
ご逝去後の相続税申告なのか、ご生前の相続税対策をご希望されているのかによって、ご用意いただくものが異なります。
⑴ ご逝去後の場合
相続税申告は、原則として亡くなった日の翌日から10か月という期限がありますので、亡くなった日がいつか分かる資料を用意していただくか、または口頭でお伝えください。
また、亡くなった方が事業を営まれていた場合は、その旨もお伝えください。
事業を営んでいた方が亡くなった場合、準確定申告が必要となるのですが、準確定申告は原則として亡くなった日の翌日から4か月以内という期限があり、早期に対応しなければならないためです。
⑵ ご生前の場合
相続税対策を検討するためには、資産内容、資産規模、相続人の関係図等が必要となります。
メモ書きでも構いませんので、これらのことが分かるものをお手元にご用意いただいた上でご相談にお越しいただければと思います。
税理士に相談する際にこうした資料をご用意いただければ、ご相談もスムーズに進み、より正確なアドバイスを差し上げることが可能です。
資料の用意が難しいこともあるかと思いますので、その場合は次回のご相談までにご用意いただくなどもできますので、税理士までお伝えください。
税理士を紹介してもらうときの注意点
1 税理士を紹介してもらったとき

税金に関する相談をしたい場合、真っ先に税理士に相談することを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
しかし、多くの税理士がいる中で、どういった税理士を選ぶかは判断に迷うことが多いです。
知人等からの紹介であれば比較的安心できますが、紹介を受けた上で、その税理士に依頼をすべきかどうかをしっかりと検討する必要があります。
税理士を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがありますので、税理士を選ぶ際の注意点をいくつか挙げていきたいと思います。
2 税理士の専門性と経験
まず、専門性の確認をする必要があります。
これは、税理士がどのような分野に強いのかを確認するということです。
特定の分野や業種に精通している税理士は、あなたのニーズにより適したアドバイスをしてくれる可能性が高いです。
次に経験と実績を確認します。
過去の実績や顧客の評判を確認し、その税理士がどの程度の実務経験を持っているのかを確認するとよいです。
例えば、相続税であれば、年に何件申告しているのか、これまで何件申告してきたのか聞くことで、ある程度実務経験を確認することができます。
このとき、紹介者の方に評判を聞きやすいのが紹介特有のメリットです。
紹介者の方と親しい間柄であれば、なおさらその評判も信頼できるのではないでしょうか。
3 コミュニケーション能力やサポート体制
顧問業務を依頼する等、場合によっては税理士と長く頻繁に付き合いが続くことになることもあります。
いくら、税務の知識が豊富でも、コミュニケーションができなければ関係を続けていくことが難しい場合もあるかもしれません。
具体的には、意思疎通がスムーズであるか、また、税務の専門用語を分かりやすく説明してくれるかどうか等を確認するのがよいです。
疑問や質問に対して丁寧に対応してくれる税理士かどうかもポイントになるかと思います。
次にサポート体制です。
どのようなサポート体制が整っているかを確認します。
テレビ電話やメールでの対応がどの程度スムーズにできるのか考慮するとよいかと思います。
今でも、連絡手段が電話やFAXのみという事務所もありますので、連絡手段やサポート体制をあらかじめ確認しておくことは大切です。
4 実際に税理士に会ってみる
これらのポイントを考慮することで、適切な税理士を選ぶことができるかと思います。
また、相性や信頼関係も重要なので、複数の税理士を比較検討し、実際に面談してみることもおすすめです。